高エネルギー励起光電子分光による価数相転移の観測
序
物質に光を当てて、飛び出してきた電子 (光電子) のエネルギーや運動量を測定することで、物質中の電子のふるまいを知ることができる。この実験手法は、光電子分光と呼ばれている。物質の性質は、本来物質中の電子の挙動で決定されているので、光電子分光は、物性の本質に迫ることのできる手段のひとつとなっている。光電子分光は 1970 年頃から、有用な実験手段として、よく行われてきたが、特にここ 10 年の間に長足の進歩をとげ、例えば、高温超伝導をはじめとして、数多くの物性の解明に、なくてはならない手段となっている。
従来、光電子分光で頻繁に用いられてきた光のエネルギーは、X 線管を除けば、概ね数 10 eV 程度の真空紫外領域であった。このエネルギー領域で励起したときの光電子は、物質のごく表面付近からしか飛び出してこないことは古くから認識されていた。このエネルギー領域では、光電子の平均自由行程が最も短く、光電子は、物質の表面近傍のみの情報しかもたらさない。光源としてよく用いられる Mg Kα 線 (1253 eV)、Al Kα 線 (1486 eV) の場合でも、光電子の平均自由行程は、物質に依存するが、1000 eV で高々 2nm 程度である。物質の中には、表面層が異常に厚いものも存在し、その場合には、平均自由行程を大きくして、物質の中の情報を探る必要がある。
これを解決するには単純に 2 つの方向がある。光電子の平均自由行程は概ね 50 eV で最小となるので、励起エネルギーを極端に小さくするか、極端に大きくして、光電子の運動エネルギーをあげてやればよい。本研究で用いた手段は後者である。後者の場合、励起エネルギーを大きくすると、光電子が放出されにくくなるため(イオン化断面積が小さくなる)、高エネルギー励起の光電子分光はこれまでほとんど行われてこなかった。最近、RIKEN、JASRI、広島大学が、数keV で励起した光電子分光 (HXPES) の確立に成功したが [1]、それには、SPring-8 のような高輝度光源の出現に多くを負っている(もちろん光電子分析器の最近の高性能化もなくてはならないファクターである)。
HXPES の確立により、新しい観測結果が次々もたらされるようになったが、我々は HXPES により、これまで分光学的実験と基本的な物性実験の結果に矛盾が指摘されてきた YbInCu4 でみられる価数相転移の観測を試みた。YbInCu4 は図 1 に示すような、C15b 型とよばれる立方晶の構造をもっている。この物質の特徴は、42 K 付近で"価数相転移"と呼ばれる珍しい現象を示すことにある。Yb 化合物中では Yb イオンの価数は 2 価 (Yb2+) あるいは 3 価 (Yb3+) であり、しばしば両者が混在する。この物質では、温度とともに Yb イオンの価数が変化する。室温では、Yb イオンはほぼ Yb3+ の状態としてふるまうことが磁化率の測定から分かっている。温度を下げていくと熱収縮により格子定数が小さくなるが、42 K で、構造不変のまま約 0.5 % 膨張する。それとともに、磁性もキュリーワイス型の常磁性から、パウリ常磁性に変化する。この膨張は、Yb2+ イオンのほうが、イオン半径が大きいため、Yb イオンの価数が 3+ から 2+ の方向に変化したことを反映していると考えられ、実際そのとおりである。このような価数状態は、格子定数の変化のような間接的な手段とは対照的に、光を用いた実験で直接観測できる。実際発見 (1986 年) 直後に Yb 2p 吸収測定が行われ価数が評価されたが、磁化率、格子定数から予想される価数とは若干異なっている [2]。例えば、室温では Yb2+ も若干混ざっているという結果が得られている。
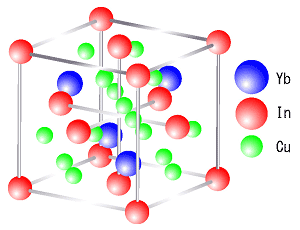
図 1 YbInCu4 の結晶構造
YbInCu4 に対する光電子分光も、発見直後から測定されてきたが、本格的な実験がなされたのはほぼ 10 年前である。h =43 eV で行われた Reinert らの実験結果 [3] によれば、Yb イオンの価数は 220 K において 2.85 であり、降温にしたがって緩やかに 2.56 まで減少するが、転移点近傍での急峻な変化はみられない。加えて価数は予想されていた値よりもかなり少ない。Reinert らはこの原因として、表面からの寄与が大きいためと結論している。そこで我々は、励起エネルギーを大きくすることで表面鈍感にすることにより、価数相転移に伴う光電子スペクトルの変化の観測を試みた。軟 x 線を用いた実験も行ったが [4]、ここでは HXPES の結果についてのみ述べる [5]。
実験
YbInCu4 単結晶は、愛媛大学大学院工学研究科の平岡耕一助教授により、フラックス法を用いて育成された。育成した試料の評価は X 線回折および磁化率測定により行った。磁化率から評価された転移の温度幅は約 2 K である。HXPES は SPring-8、BL29XU で行った。アンジュレータ光は、Si(111) 二結晶および Si(333) チャンネルカットで 6 keV に分光され試料に照射される。用いた光電子分析器は HXPES 用に改良された VG シエンタ社の SES2002 である。
実験結果および考察
まず最初に Yb 3d 内殻スペクトルの温度依存性を図 2 に示す。横軸はフェルミ準位を基準とした結合エネルギー、縦軸は光電子放出強度である。Yb 3d 内殻はフェルミ準位より下 1500-1600 eV に位置しており、従来の X 線管を用いた実験では励起することのできなかった内殻である。スペクトルは 3d 内殻のスピン軌道分裂により、1515-1540 eV の 3d5/2 領域と、1560-1585 eV の 3d3/2 領域にわかれる。更に各領域は 2 つに構造に分かれ、いずれも低結合エネルギー側が Yb2+、高結合エネルギー側が Yb3+ による構造に帰属される。ここで、Yb2+ および Yb3+ による構造が、はっきりと分離して観測されているのが、後の解析にとって重要である。Yb 価数の違いにより、3d 内殻が異なるエネルギーに観測されるのは、Yb 原子の電子数が、Yb3+ のほうが少ないため、Yb 原子内でのクーロン反発が小さくなり、安定化するためである。また、Yb3+ による構造は、Yb2+ の構造が単一のピークであるのに対し、複雑な形状をしている。Yb イオンの価数の違いは、価電子帯に存在する 4f 軌道の占有率の違いと等価であり、Yb2+ イオンでは全ての 4f 軌道が占有されているのに対し、Yb3+ イオンでは、4f 軌道がひとつ空いている。このひとつ空いた Yb3+ イオンの 4f 正孔と、3d 内殻励起後の 3d 正孔がクーロン相互作用するため、このような複雑な多重項構造が現れる。この構造の複雑さからも、高結合エネルギー側が、Yb3+ イオンによる構造であることが分かる。
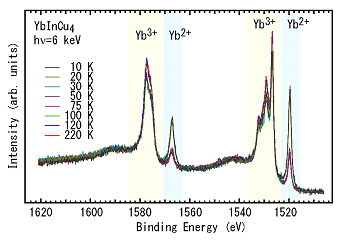
図 2 YbInCu4 の Yb 3d 光電子スペクトル
目的であった温度変化に注目すると、転移点である 42 K をはさむ 50 K と 30 K の間で顕著に観測されていることが分かる。特に Yb2+ による構造が、30 K 以下で急激に伸びている。このことは、転移点通過後に YbInCu4 における Yb2+ の成分が急激に増加したことを示している。同じく Yb3+ による構造の強度は減少しており、このことを更に裏づけている。つまり、価数相転移が、Yb 3d 内殻スペクトルに、明瞭に観測されていることになる。このような急峻な変化は、これまでの真空紫外 [3]、軟 x 線 [4] を励起光とした光電子分光では観測されていない。
Yb2+、Yb3+ による構造の強度から、各温度における Yb の平均価数を求めることができる。平均価数を求めるためには、単純に各構造の面積強度比を求めてやればよい。そのために、図 3 に示すようなカーブフィッティングを行った。Yb2+ による構造はひとつの準位で、Yb3+ による構造は Yb イオンに対して計算された多重項を用いた。1540、1590 eV にブロードな構造があるが、プラズモンによる構造だと考えている。図 3 からわかるように、単純な仮定にもかかわらず、フィッティングの度合は概ねよい。
フィッティング結果から求めた Yb 価数を温度の関数として 図 4 に示す (Yb 3d HXPES)。価数は転移点より上で約 2.90 であり、50 K までほとんど一定、転移点で急激に 2.74 まで減少すると見積もられた。図では、物性測定から予測されている値 (Thermodynamic data)、真空紫外領域 (VUVPES) [3]、軟 x 線領域 (SXPES) [4] で励起したときの光電子分光実験より評価された値と比較した。後者の光電子分光では、Yb 価数は、価電子帯に現れる Yb2+ 4f と Yb3+ 4f による構造の強度比から導かれた (図 5 参照)。光電子分光の結果に限れば、今回の HXPES だけに、転移点において、急峻な変化が観測されていることが分かる。
hν=43 eV, 800 eV, 6 keV における光電子の平均自由行程は、それぞれ、5、15、75 Å と見積もられる。図 4 から、平均自由行程が大きくなるに従って、転移にともなう価数の変化が急峻になること、そして、価数が物性測定から得られる値に近づいていることがわかる。このことは、YbInCu4 本来の明瞭な価数相転移を直接観測するためには、励起エネルギーを大きくして、光電子の平均自由行程を大きくする必要があったことを示している。光電子スペクトルの励起エネルギー依存性は、YbInCu4 には比較的厚い表面領域 (subsurface) が存在すると考えることにより説明できる。すなわちその領域では YbInCu4 本来の価数より 2+ に近いこと、また、転移点が 42 K よりも高く、かつ広く分布していることが考えられる。
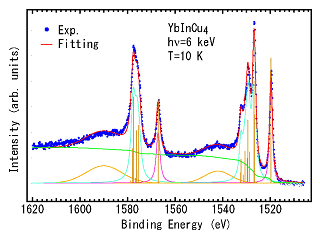
図 3 Yb 3d 光電子スペクトルを用いた YbInCu4 の価数評価
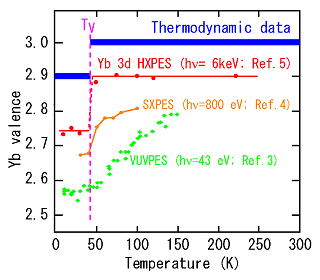
図 4 YbInCu4 の価数評価の比較
最後に価電子帯スペクトルを図 5 に示す。スペクトルの構造は、図中に示したように帰属される。Yb 3d スペクトル同様に、転移点である 42 K をはさむ 50 K と 20 K の間で急激に変化し、20 K では、フェルミ準位近傍に Yb2+ 4f による 2 つのピーク構造が、顕著に伸びていることが分かる。これはもちろん転移点以下で Yb2+ 成分が増えたことに由来しているが、ここで注目すべきことは、50 K、220 K のスペクトルには、このピーク構造はほとんど観測されず、高々名残のようなものが残っているに過ぎないことである。一方 Yb 4f が強調されて観測される軟 x 線領域 (h =800 eV) で測定したスペクトルには、42 K 以上でも、ピーク構造がかなりの強度をもって存在し、このことが、図 4 において、価数を下げる原因になっている。
HXPES では、価電子帯スペクトルから Yb 価数を評価することは困難である。転移点より上において、Yb2+ 成分がほとんど観測されないのがその理由である。しかし、励起エネルギーにかかわらず、価電子帯には Yb 4f 以外に Cu 3d 軌道をはじめ、様々な伝導電子スペクトルに寄与する。一方 Yb 3d スペクトルは、その領域において、Yb 3d 以外の成分は寄与しない。したがって、価数の評価には Yb 3d スペクトルを用いるほうが、精度が高くなると期待できる。このことは Yb 化合物のみならず、他の希土類化合物にも適用され、HXPES の希土類 3d 内殻スペクトルは、価数評価の手段を与えるものとして今後が期待される。
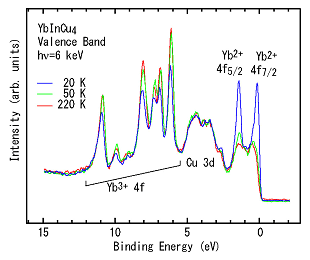
図 5 YbInCu4 の 価電子帯光電子スペクトル
参考文献
[1] K. Kobayashi et al., Appl. Phys. Lett. 83, 1005 (2003); Y. Takata et al., Appl. Phys. Lett. 84, 4310 (2004).
[2] I Felner et al., Phys. Rev. B 35, 6956 (1987).
[3] F. Reinert et al., Phys. Rev. B 58, 12808 (1998).
[4] H. Sato et al., Phys. Rev. B 69, 165101 (2004).
[5] H. Sato et al., Phys. Rev. Lett. 93, 246404 (2004).











