内殻励起有機分子の選択的結合切断と分子変形
概要
国立大学法人広島大学大学院理学研究科、広島大学放射光科学研究センター研究員の平谷篤也教授、吉田啓晃助教の研究グループは、放射光科学研究センター[センター長(事務取り扱い):生天目博文](以下「HSRC」)の放射光施設(以下「HiSOR」)を用いて、いくつかの有機分子について新たな励起状態選択的解離過程を発見した。特に、アルコール分子の酸素原子の内殻軌道から特定の非占有軌道への励起では内殻励起状態でオージェ過程と競合する超高速解離過程、あるいは内殻励起状態での分子変形に誘起されたイオン性解離過程によってそれぞれの励起状態に特徴的な選択的解離が起きることを初めて明らかにした。
原子に局在する内殻電子軌道から反結合性の価電子軌道への励起では、内殻励起状態の極めて速い電子緩和過程である"オージェ過程"と競合して分子結合の切断、いわゆる超高速解離が起きることは、原子間結合がひとつのみである塩化水素などの二原子分子ではよく知られていたが、多数の原子から構成される有機分子では結合の種類と数が多く、質量数が接近した解離イオン種を分離して検出することができない場合が多く、内殻励起状態での超高速解離を実験的に証明することはであった。本研究の成果は内殻励起有機分子から生成する、運動エネルギーを持った解離イオン種をこれまでにない高い質量分解能で検出し、内殻励起解離過程によって生成する解離イオンをすべて分離測定できたことによるものである。さらに、いくつかのアルコール分子についての測定を行うことにより、超高速解離によって生成が促進される解離断片分子からアルコール分子に共通した特徴的な解離イオンが生成することを示した。
背景
紫外線による日焼けのように光による物質の変化(光反応)は日常生活で問題となるだけでなく、宇宙ができてから現在までの分子進化とその解明にとっても重要な役割を果たしている。このような光反応は現在の銀塩写真の基礎となった銀化合物の光分解を初めとして18世紀から研究され、19世紀末からは種々の有機化合物の光化学反応として発展した。特に、20世紀後半にはレーザーの発見と分光学・光化学への応用によって、光化学反応の研究は質、量ともに飛躍的な発展を遂げた。さらに、光化学反応研究へのレーザー利用の進展とほぼ同時期に、高速電子から放出され、赤外線からX線までの広いエネルギー範囲をもつ放射光の利用が可能となり、光化学反応の対象となる光のエネルギー範囲はレーザーの限界であった紫外線領域からX線領域まで、100倍以上に拡張された。特に、レーザーなどの可視・紫外光源とX線管などの硬X線源の間に位置し、多くの原子の内殻電子励起が可能となる軟X線領域では、放射光が唯一のエネルギー可変光源であることから、内殻電子励起による光化学反応の研究は、放射光によって初めて可能となった。
原子核近傍に局在する内殻電子は、物質の多彩な構造や性質を決めている外殻の価電子とは異なり、化学結合に関与せず、分子内の特定の原子に固有の束縛エネルギーをもっている。多くの有機分子を構成する炭素、窒素、酸素の内殻軌道の束縛エネルギーは、それぞれ〜290 eV、〜400 eV、〜530 eVである。そこで、軟X線領域の光のエネルギーをその結合エネルギーに合わせることにより、特定の原子に局在した内殻電子のみを選択的に励起することができる。内殻電子そのものは結合に関与しないが、内殻電子が励起された場合には、次のような過程で分子結合の切断が起きる。内殻励起により生成した内殻正孔に価電子起動の電子が落ち込み、その際の余剰エネルギーでさらにもう1個以上の電子が放出されるオージェ過程が短時間(10−15 〜 10−14 s)に起き、価電子軌道上に2個以上の正孔を生じる。この過程で生じる分子イオンは一般にエネルギーの高い状態であり、いくつかの原子間結合が切断される。特に、これらの正孔が結合性価電子軌道に生じた場合や化学結合の両端に局在した場合には、正の電荷を持つ原子核間の反発に抗して原子を結び付けていた電子が無くなるために、大きなクーロン反発力が結合原子間に働き、短時間(10−14 〜 10−13 s)にその結合の切断が起こる。オージェ過程は内殻励起原子の近傍で起きることから、結合性価電子軌道や結合の両端に正孔を生じる軌道配置が局在化している分子系では、内殻励起された原子が関与する結合の切断が選択的に促進される。さらに、内殻電子軌道からの励起先軌道が特定の結合について反発的であるような内殻励起状態では、オージェ過程と競合する超高速解離が起きる。このような内殻励起原子選択的反応や励起状態選択的反応は内殻励起反応の最大の特徴であるが、有機分子での選択的反応の程度やその発現機構の詳細は未だに解明されていない。

図 1 HiSORビームラインBL-6に設置された角度可変高分解能イオン質量分析装置。
研究内容
内殻励起状態は有機分子のイオン化しきい値を遥かに超えた高いエネルギー状態であるため、ほぼ100%の確率で1個以上の電子を放出してイオン化する。さらに、イオン化後の分子内部に残されるエネルギーは複数の結合を切断するのに十分であることから、種々の解離イオン種が生成する。これらの解離イオン種の生成量は内殻励起状態での解離過程や、オージェ過程後のイオン化状態からの解離過程に関する詳細な情報を与える。しかし、内殻励起有機分子から生成する解離イオン種は大きい運動エネルギーを持つことから、CO+とCOH+など1質量単位だけ異なるイオン種の生成量を正確に求めることは困難であった。この問題に対して、独自に開発したリフレクトロン型飛行時間質量分析器を用いることによって、内殻励起解離過程によって生成する解離イオンをすべて分離測定し、個々の内殻励起状態に特有の解離過程を同定した。
図2にメタノール(CDH3OH)のメチル基の水素を重水素で置換したCD3OHについて、酸素1s内殻励起領域の2つの励起エネルギーでの解離イオン種の分布を示した。他の励起状態からの解離イオン収率は3pa'励起とほぼ同様であるが、3sa'励起ではO-H結合を持つOH+とCOH+イオンの収率が減少しており、O-H結合の切断が促進されることを示している。O1s-3sa'励起状態はO-H反結合性であることが知られているが、この観測結果からだけでは内殻励起状態でO-H結合が切断されてからオージェ過程によってイオン化したのか、特定のオージェ過程によって生成したイオン化状態からの解離過程でO-H結合切断が促進されたのかを結論することはできない。この点を解明するために、オージェ過程によって生成する多くのイオン化状態からの解離イオン種について同様の測定を行った。その結果、3sa'励起ではオージェ過程で生成するオージェ終状態とは無関係にO-H結合の切断が促進されていることを見出した。このことから、3sa'内殻励起状態においてはオージェ過程と競合するO-H結合の超高速解離が起きていることが結論付けられた。内殻励起状態でのO-H結合切断によって酸素原子に内殻正孔を持つCD3O*が生成し、オージェ過程によって励起状態のCD3O+イオンとなる。CD3O+イオンは不安定であり、DCO+とH2に解離する。これが3sa'励起によるDCO+の増加の原因と考えられ、実際にDCO+の増加量はOH+とCOH+の減少量と良く一致している。これらの結果は、有機分子の内殻励起状態での超高速解離過程を実証しただけでなく、超高速解離によって誘起される新たな内殻励起状態選択的反応の存在を示したものである。一方、3sa'励起で増加するCD3+の増加量はOH+とCOH+の減少量より大きく、内殻励起状態でのO-H結合切断とその後のオージェ過程を経たイオン性解離だけでは説明できない。537.5eVの3pa"励起状態におけるCO+、COH+、DCO+の減少とCD3+の増加を含め、実験的に観測された解離過程の励起状態依存性の機構を解明するためにメタノール分子の内殻励起状態での原子間結合力の変化を分子軌道計算によって求めた。図4に示したようにO−H結合は3sa'状態のみで反発的となっており、H原子が軽いため結合の伸びが速く、オージェ過程と競合する超高速解離過程が起きる。一方、C−O結合は3pa"状態で強い反発型となっているだけでなく、3sa'状態でも反発型となっている。3pa"状態でのC−O間の反発力(ポテンシャル曲線の傾き)は3sa'状態でのO−H間反発力より大きいが、C原子とO原子の質量が大きいためにC−O結合が伸びる速さが遅くなることから、内殻励起状態でC−O結合は伸びるものの、解離に至る前にオージェ過程が起きる。以上のことから、3sa'状態でのCD3+の増加、および3pa"状態でのCD3+の増加とCO+、COH+、DCO+の減少は、内殻励起状態でのC−O結合の伸張という分子変形によって、オージェ過程後のイオン性解離における生成効率が変化したためと結論できる。
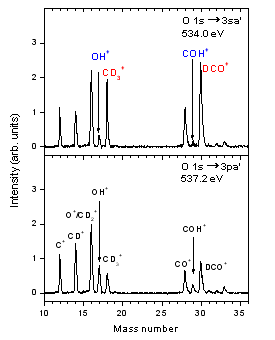
図 2 重水素化メタノール(CD3OH)の酸素1s内殻励起によって生成する解離イオン種の分布。他の励起エネルギーでは下の537.2eV励起と同様の分布である。一方、上の534eV励起では、わずかな励起エネルギーの変化にもかかわらず、OH+とCOH+が減少し、CD3+とDCO+が増加している。
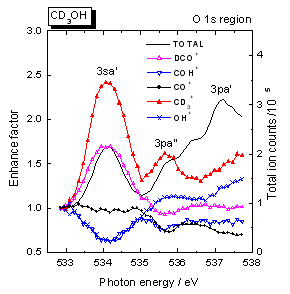
図 3 重水素化メタノール(CD3OH)の酸素1s内殻励起領域における解離イオン種生成効率を酸素の内殻励起が起きない532.8eVを基準として表したイオン収率スペクトル。黒い実線は吸収スペクトルに対応する全イオン収量スペクトルである。3sa'励起(534.0eV)では、OH+とCOH+イオンの収率が30%程度減少する一方、CD3+は2.5倍、DCO+も1.7倍増大している。3pa"励起(535.7eV)ではCD3+が増加し、C-O 結合を持つCO+、COH+、DCO+が減少する。
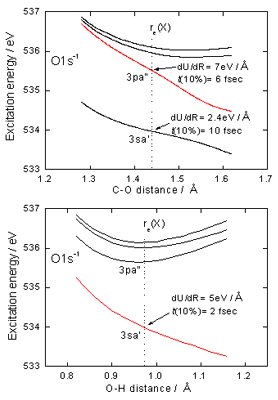
図 4 メタノール(の酸素1s電子をいくつかの空軌道に励起した場合の結合エネルギーのC-O結合距離(上図)とO-H結合距離(下図)に対する依存性の分子軌道計算結果。O-H結合は3sa'励起で強い反発型となり、オージェ寿命(3fsec)より短い2fsecで10%程度伸長する。一方、C-O結合は3sa'励起で弱い反発型、3pa"励起で強い反発型となる。
本研究の意義
宇宙における分子進化では、光化学反応によって生成した解離イオンと中性分子のイオン−分子反応が重要な役割を果たしている。特に、高濃度の星間分子雲では、分子雲内部まで到達しうる軟X線によるイオン性解離過程が解離イオンの主たる供給源となることから、軟X線のエネルギーによって解離イオンの分布がどのように変化するかを知ることは、分子雲内部での分子進化を解明するうえで重要な鍵となる。応用科学の面でも、励起する軟X線のエネルギーをわずかに変えることによって、特定の解離イオン種の優先的な生成や、生成イオン種の割合を変えることができるため、対象となる分子系を拡張することによって、軟X線による分解生成物を用いたCVD(化学気相成長)による機能性薄膜の創製や表面修飾への応用が期待できる。











