Bi(001)表面のRashbaスピン分裂の直接観測
はじめに
超消費電力の論理演算素子として、半導体超格子界面に2次元電子ガスに、強磁性金属をソースとドレインとして半導体中に「スピン注入」することで、ゲート電圧によってスピン回転角決定し、その結果ソース・電流を制御できるという画期的なアイデアが1990年にDattaとDasによって提唱された。ここで重要となるのは、Rashbaスピン分裂と呼ばれ、対称性の破れから生じる物理現象が重要な鍵となっている。
このような,半導体二次元電子ガスにおけるRashbaスピン分裂を直接光電子分光で評価するのはいまのところ困難であるが、例えば、金属単結晶表面上における表面電子状態が2次元電子ガスであることに注目すると、スピン軌道相互作用の比較的大きな重い元素についてはそれを観測することができる。最近ではAu(111)単結晶表面上でそれが観測された。またその他に、SbやBiといった半金属単結晶表面や薄膜でそれらが、(スピン分解しない)ARPESによって観測されたという報告がある。しかしながら、それを直接的に検証するためには「スピンを分離」して観測することが必須である。そこで本研究ではSi(111)表面上のBi(001)超薄膜に対してスピン角度分解光電子分光(SRARPES)を行い、スピン分裂を直接検出した。

図 1 DattaとDasが提唱したスピン電界効果トランジスタ(Spin-FET)。
スピン・角度分解光電子分光
図2にはスピン・角度分解光電子分光の概略図を示す。スピン分解光電子分光では光電子エネルギー分析器のうしろにスピン検出器を取り付けた構成になっている。スピン検出器にも様々な種類のものが存在するが、ここでは比較的取り扱いが容易で、一番ポピュラーな「モット型スピン検出器」について解説する。モット型スピン検出器はいわゆる相対論的な電子のモット散乱という物理現象を利用したものである。高速で加速されたスピン偏極した電子がターゲット原子で後方散乱された後、左右に検出される散乱電子数(ここではそれぞれNL , NR とおく)に差が生ずるというものである。このモット散乱は、ターゲット原子の大きなスピン−軌道相互作用によって引き起こされる。この NL と NR の非対称性 A=(NL-NR)/(NL+NR) を定義すると、入射電子のスピン偏極度 P=(N↑-N↓)/(N↑+N↓) (ここでN↑とN↓はそれぞれアップおよびダウンスピン電子数を示す)は有効シャーマン関数 Seff と呼ばれる装置固有のスピン検出能を用いて P=A/Seff と表せる。
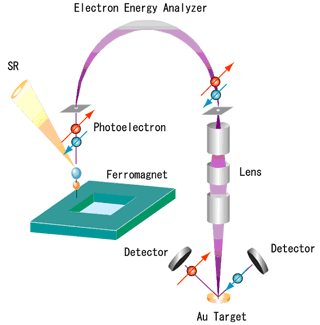
図 2 スピン・角度分解光電子分光の概略図。
実験結果・考察
実験は広島大学放射光センターのSRARPES装置で行った。図3(a)に実験配置を示す。図3(b)および(c)から分かるようにアップとダウンスピンは明確に分裂しており、Γ点に関して反対称な構造をしていた。さらには、図4に示すようにΓ点から離れたところでも、明確にスピンの反対称構造が明確に観測できた。図5(b)には、理論的に予測されたBi(001)表面のバンド構造とそのスピン偏極度を示す。一方、図5(a)には今回のSARPES実験で得られた結果をエネルギー分散関係とスピン偏極度として載せている。この結果から、実験と理論計算との良い一致が得られたことが分かる。
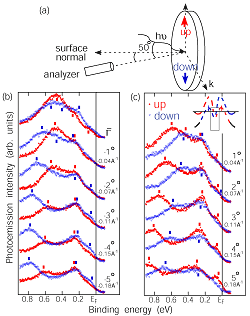
図 3

図 4
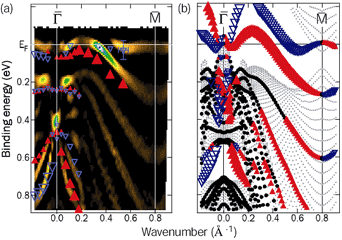
図 5











